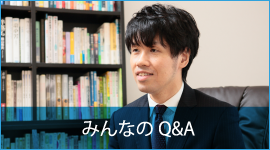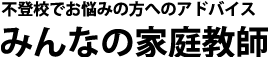活動報告
新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか❶
2015/06/152015年5月27日、不登校の子供たちが、家庭やフリースクールで行なう学習を義務教育と認める法律の試案が、フリースクールと夜間中学校の合同議員連盟総会で発表されました。
早ければ法案の施行は、再来年度の2017年度からとなるそうです。
文部科学省は、不登校の小中学生が約12万人いる現状を踏まえて、フリースクールで学ぶ生徒を支援する方向で、有識者会議を設けました。法案は、「多様な教育機会の確保」という考えに基づくものであり、その対象を「様々な事情により、学校で義務教育を十分に受けていない者(年齢、国籍を問わず)」と定めました。
保護者が子供と合意して、学校以外で学ぶことを選んだ場合、地元の教育委員会や学校等から助言を得て「個別学習計画」を作り、教育委員会に申請します。そして、教育委員会の「教育支援委員会(新設)」がそれを審査し認定します。
学習計画を実施した後、教育委員会が修了認定を発行します。これにより、保護者は子供に対する就学の義務を履行したものとみなされ、子供は高校への進学が可能となる流れです。また国や自治体は、家庭への経済的支援も検討するという内容です。
不登校の子供たちへの対策を、これまでの学校復帰一辺倒から、学校以外の場所で学ぶことも可能である、と明確化したことは画期的だと思います。
フリースクールまたは自宅での学習が、義務教育制度の一環であると認められることは、不登校の子供や保護者、そして学校関係者にとっても希望の光となるのではないでしょうか。
次回へ続く。
不登校だった生徒の「その後」❸
2015/06/08不登校を経験した生徒の多くが、卒業後も人間関係に不安を抱えているということが、文部科学省の調査で明らかになっています。
また、調査で「中学校3年生の時にあれば良かったのに」と思ったことを振り返ってもらったところ、「こころの悩みについての相談」と並んで、「自分の気持ちをはっきり表現したり、人と上手につき合ったりするための方法についての指導」という答えが3人に1人の割合にのぼったそうです。
もともと人づき合いが苦手だったことに加え、長期間学校を休んでしまい、人とつき合う機会が少なくなってしまったことにより、苦手な人づき合いを克服する機会をもてなかったことを反映しています。
不登校になった後、職に就くことができずにいる若者の支援をしている人たちに聞くと、こうした若者の多くは人と目を合わせたり、挨拶をしたりすることに慣れていないようだと言います。
また、心の中では人と交わりたいという潜在的な思いはあるものの、なかなか一歩を踏み出せずにもがいているようだとも言います。
対策としては、趣味を通したサークル活動に参加したり、短期のアルバイトに挑戦したり、地域の行事やボランティア活動に参加したりすることが有効だと考えられます。
そこで出会った人たちから、「ありがとう」と声をかけられることで、自己肯定感が少しずつ高まることも期待できます。
大切なことは、一歩前に踏み出そうとする本人の勇気と、長い目で見守りながら、そっと背中を押してあげられる家族や地域の大人の存在なのではないでしょうか。
不登校だった生徒の「その後」❷
2015/06/01一つは、高校進学を考える時に、全日制の高校だけでなく、定時制や通信制の高校まで選択肢を広げること、決断は生徒自身がすることが大切です。
高校=全日制、というこだわりを捨てて、本当に自分に合った高校を生徒本人が選ぶことは、高校に通い続けるうえで、非常に意味があります。
一つの例として、親が子供に全日制の高校へ行くよう強引に勧めた後に、入学した高校で不登校が再発したケースがあります。その時に、子供が絶望感に襲われ、「親のせいでこうなったんだ」と、家庭内暴力に発展したことがありました。
このように、本人が望まない高校への進学は、かえって事態をこじらせる可能性を高めてしまいます。最終的には、子供自身が決断し、親はそれを尊重することが重要です。
もう一つは、「子供のために、親が本当の意味での味方になることができるか」です。
不登校の生徒と話をした時に、よくこんな声を耳にします。
「親はどうでもいい時に口出しするくせに、力になって欲しい時には全然かまってくれん」
親は、どんな時に子供の力になればいいのか、背中を押してあげればいいのかを、しっかり見極める必要があります。
不登校を経験した生徒が高校進学後に、不登校を再発する可能性もあります。その時に、親がどんな対応をするかで、その後が大きく変わっていきます。
無理に学校へ行かせようとするのか、それとも子供の気持ちに寄り添い、話にじっくり耳を傾ける姿勢をとるのか。非常に重要な分岐点になります。
「親」という漢字のように、木の陰に立ってそっと子供を見守る、という姿勢で接することが求められます。
不登校だった生徒の「その後」❶
2015/05/27学生時代に、不登校を一定期間経験した生徒の「その後」はどうなっているのでしょうか?
約7〜8割の生徒は、何らかの形で学校生活に復帰できています。また、学校生活に戻らないとしても、アルバイトを始める人もいます。不登校を経験したほとんどの生徒が、勉強したり働いたりする機会を得て社会と関わっています。いわゆる、家に完全にひきこもる人は、少数派といえます。
しかし、不登校だったゆえの問題点もあります。ある生徒は、二度と不登校を経験したくない気持ちから、高校進学後、無遅刻無欠席で学校へ通い続けました。
「とにかく学校へ通わなければ」と、本人も相当に無理をし、家族もそれを期待しました。
そして、二ヶ月経過した時に、突然学校へ行けなくなってしまいました。無理をし続けたために息切れを起こしたのです。
不登校が再発したことで挫折感が大きいため、本人も家族も、以前にも増してがっかりし、絶望感に襲われました。
このようになってしまうと、長期間こじれる原因の一つになってしまいます。
「毎日学校へ通えないなら、将来の仕事も長続きしないのでは。。。」と、マイナス思考に陥る危険性もあります。
では、中学に不登校を経験した場合、その後の高校進学は、どのような点に注意が必要でしょうか?
次回へ続きます。
不登校とHSP❸
2015/05/16今回は、HSPを理解するために、長所と短所と思われる部分について考えてみようと思います。
HSPの長所と思われる部分
①細かいところに気が付く
②想像にふけることが割と多く、記憶力が比較的高い
③退屈があまり苦痛ではない
④慎重で危険や失敗を回避できることが多い
⑤他人の気持ちに共感できる
⑥優しく温和である
HSPの短所と思われる部分
❶騒音や強い光、痛みや臭いなど、五感からの刺激に弱い
❷悪い結果を想像してしまったり、過去の嫌な出来事を思い出して悩むことが割と多い
❸ジェットコースターやホラー映画など、刺激の強い娯楽が苦手である
❹新しいことを始める時、尻込みしてしまう
❺周囲の人間の顔色をうかがい、彼らの気分に大きく左右されやすい
❻内気に見えやすく、活気がないように思われやすい
長所と短所、まず6つずつあげてみました。
それぞれの6つの数字は、裏表の対になっています。
例えば、①「細かいところに気が付く」ということは、❶「騒音や強い光、痛みや臭いなど、五感からの刺激に弱い」ということになります。
この他にも長所として、芸術作品などに感動しやすい、があります。短所としては、緊張しやすかったり、不眠、腹痛などの心因性の症状になりやすい、世の中の少数派であるといった点があげられます。
これらの長所や短所を知ることで、それぞれが自分自身を守り、または親として子どもを守り、どのように「敏感さ」と共存し、活かしていくかを考えることが必要になります。
敏感や繊細な部分は、少しずつ刺激を与えることで耐性のようなものができて、徐々に鍛えていくことができると言われています。
したがって、HSPの持つ長所を活かし短所を補うような生き方を、早い段階から目指していくことが大切なのではないでしょうか。
そうすることが、不登校の対策につながるのだと思います。
不登校とHSP❷
2015/05/07不登校を少なくするために大切なことは、多くの人たちがHSPについて正しく理解することです。
HSPを正しく理解することによって、自分に合った環境、学校や職業を選ぶことができます。
例えば、HSPである子供(HSC=Highly Sensitive Children)の場合、HSPの存在を知り、正しく理解して生きていくのと、HSPの存在を全く知らない状態で生きていくのとでは、環境や学校、その先の職業の選択も含めて、生き方が180度変わってくるでしょう。
騒がしい都市の学校が嫌なら、静かな地方の学校を選べます。人数規模の大きい学校に通うことが苦痛なら、人数規模の小さい学校に通うことを選べます。こうして、HSPを理解することで、適応できる環境や学校を意識的に選択することが可能になり、不登校になりにくくなります。
また、HSPである子供(HSC)を持つ親の場合、HSPのことについて全く知らなければ、子育てについて必要以上に悩んだり、子供と分かりあえず衝突する機会が増えます。一方で、HSPについての知識があれば、子供と適切にコミュニケーションをとれる時間が増えます。
HSPである子供(HSC)の話に共感し耳を傾ける機会を増やすことは、学校で感じるであろう子供のストレスを和らげ、不登校になる可能性を低くできます。また、子供の進路について話し合う際、HSPを考慮しつつ、本人に合った環境、学校や仕事を、子供と一緒に考えることができます。
したがって、自己肯定感という点から考えても、本人や周囲の人たちがHSPを正しく理解すること、それが自己肯定感を高めることにつながります。
つまり、HSPの知識を正しく理解すること自体、不登校の対策をおこなうことになり、不登校に対して絶望的に悩んだりする人の数を減らすことができるでしょう。
次回へ続きます。
HSP自己診断テスト
2015/05/01HSP自己診断テスト
次の質問に、感じたまま答えてください。
少しでも当てはまるのなら「はい」と答えてください。
まったく当てはまらないか、 あまり当てはまらない場合に「いいえ」と答えてください。
1.自分をとりまく環境の微妙な変化によく気づくほうだ
2.他人の気分に左右される
3.痛みにとても敏感である
4.忙しい日々が続くと、ベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ、刺激から逃れられる場所にひきこもりたくなる
5.カフェインに敏感に反応する
6.明るい光や強い匂い、ざらざらした布地、サイレンの音などに圧倒されやすい
7.豊かな想像力を持ち、空想に耽(ふけ)りやすい
8.騒音に悩まされやすい
9.美術や音楽に深く心動かされる
10.とても良心的である
11.すぐにびっくりする(仰天する)
12.短期間にたくさんのことをしなければならない時、混乱してしまう
13.人が何かで不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐに気づく (たとえば電灯の明るさを調節したり、席を替えるなど)
14.一度にたくさんのことを頼まれるがイヤだ
15.ミスをしたり、物を忘れたりしないようにいつも気をつける
16.暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている
17.あまりにもたくさんのことが自分のまわりで起こっていると、不快になり、神経が高ぶる
18.空腹になると、集中できないとか気分が悪くなるといった強い反応が起こる
19.生活に変化があると混乱する
20.デリケートな香りや味、音、音楽などを好む
21.動揺するような状況を避けることを、普段の生活で最優先している
22.仕事をする時、競争させられたり、観察されていると、緊張し、いつもの実力を発揮できなくなる
23.子供のころ、親や教師は自分のことを「敏感だ」 とか 「内気だ」 と思っていた
以上の質問のうち12個以上に「はい」と答えたあなたはおそらくHSPでしょう。
しかし、どの心理テストも、実際の生活の中での経験よりは不正確です。
たとえ「はい」がひとつかふたつしかなくても、 その度合いが極端に強ければ、そんなあなたもHSPかもしれません。
以上、「ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。」より抜粋
エレイン・N・アーロン [著]・ 冨田香里 [訳]
不登校とHSP❶
2015/04/30HSP
聞きなれない単語かもしれませんが、不登校について知るために、HSPを理解する必要があります。不登校になる多くの人たちが、HSPである可能性があるからです。
HSP(Highly Sensitive Person)とは、「とても感受性が強く敏感な人」という意味です。
これは、「気質」であり「病気」ではありません。例えるならば、血液型の一つのように、人間をタイプ別に表すものです。
全人口の約5人〜6人に1人、約15〜20%の割合で存在すると言われていますので、きっと身近にHSPの人はいると思います。あるいは、あなた自身がHSPかもしれません。
HSPは、HSPでない人(非HSP)より多くのことを感じ取ることができますが、感受性が強すぎるために、傷つきやすく繊細な部分があります。 傷つきやすく繊細というと、内向的と思われるかもしれません。
しかし、HSP=内向的というわけではありません。内向的かどうかは、生まれた後の育った環境によって決まるもので、生まれつきのものではありません。外向的なHSPの人も存在します。
HSPの脳は、より深く情報を処理し考えることができるので、とても些細なことに気がつきます。 そのため、身の周りで発生する様々な物事に対して、非HSPよりも大きく驚いたり、すぐに圧倒されてしまう傾向があります。
学校という場所で考えると、少人数から多人数のクラスに変わった時に混乱したり、授業の進むスピードについていけなかったり、競争させられることで緊張し実力を発揮できなかったりと、HSPは非HSPよりも多くのストレスを感じてしまいます。
それゆえ、長期間にわたって学校に通うことが苦痛になりやすく、休みたいと思う日が多くなります。 休みがちになった時に、家族や周囲の人たちから学校へ行けないことを責められると、自己肯定感が低くなってしまいます。
自己肯定感が低くなると、学校に通うことから、さらに遠ざかってしまうという悪循環になります。
次回へ続きます。
不登校を少なくするために❸
2015/04/23前回に引き続き、幼少期からの自己肯定感を高めるために、どうすればよいでしょうか?
もう一つは、「子供の話に耳を傾け、気持ちに共感すること」です。
嬉しい時も悲しい時も、子供の気持ちに寄り添い、しっかり話に耳を傾けることで、「自分は愛されているんだ、大切にされているんだ」と自分の存在に自信を持ち、自己肯定感が高まります。
子供は、ある程度の年齢に達すると、「自立する時期」にさしかかります。親より友達に悩みを打ちあけたり、気持ちを共感してもらったりする機会が多くなります。
しかし、子供が親に何かを相談した時、子供の気持ちに共感しながら話を聴くことを怠ると、自立とは違う意味で子供が離れてしまいます。
例えば、子供が進路の相談をしてきた時に、子供の気持ちに共感せず、「その場合は〜すべきだ」「こうしたほうが、お前の将来のためだ」と言ったとしたらどうでしょうか?
親の立場から、大切な子供のためを思って、そのように言ったのかもしれません。
ところが、そう言ったことで子供の決断を尊重しなかったことになり、子供としては「親に相談してもムリ」となってしまいます。その結果、「うちの子供は、何も話してくれない」と嘆く原因の一つにつながります。
一方で、子供の話に耳を傾け、気持ちに共感することは、「いざという時は親に相談すればいいんだ」という安心感を子供に与えます。それは、自己肯定感を高め、直面するであろう不安や恐れを和らげるために、大いに貢献するでしょう。
不登校を少なくするために、そして幼少期から自己肯定感を高めるために、
◎「〜してくれてありがとう」を積極的に使うこと
◎子供の話に耳を傾け、気持ちに共感すること
次回は、HSP(highly sensitive person)について紹介します。
不登校を少なくするために❷
2015/04/15一般的に、不登校になりやすい生徒には、いくつかの特徴があります。
◎言葉に敏感である
◎感受性が強い
◎繊細で傷つきやすい
これらの特徴は、もともとの気質に加え、幼少期の環境によってその傾向が強まり、自己肯定感が低くなりやすいと言われています。(最近では、これらの特徴を持つ人を、HSPやHSCという言葉で表現することもあります。これについては、近いうちに改めて説明します)
自己肯定感とは、「自分は誰かに必要とされている人間なんだ、愛されている存在なんだ」と、自分の良い部分はもちろん、自分のダメな部分、恥ずかしいと感じる部分の全てをひっくるめて肯定できる感情のことを言います。
自己肯定感が低いことによって、不安や恐れに遭遇した時、激しく落ち込むことが多くなります。その結果、学校へ通い続けようとする気持ちを保つことが難しくなり、不登校になる可能性が高くなります。
したがって、幼少期から自己肯定感を高めていく必要があります。
では、どのようにして子供の自己肯定感を高めればよいでしょうか?
一つは、「〜してくれてありがとう」を積極的に使うことです。
「ありがとう」という言葉は、お礼の言葉であると同時に、相手の存在価値を高めてくれる言葉です。「ありがとう」を言われる回数に比例して、「誰かの役に立った」と感じる充実感が高くなります。それが自己肯定感を高めることにつながります。
次回は、その他の方法について説明します。
月別アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (5)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (1)
- 2020年9月 (3)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (7)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (21)
- 2020年2月 (29)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (16)
- 2019年11月 (16)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (17)
- 2019年8月 (16)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (24)
- 2019年5月 (33)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (11)
- 2019年1月 (10)
- 2018年12月 (11)
- 2018年11月 (20)
- 2018年10月 (22)
- 2018年9月 (38)
- 2018年8月 (43)
- 2018年7月 (28)
- 2018年6月 (26)
- 2018年5月 (21)
- 2018年4月 (23)
- 2018年3月 (24)
- 2018年2月 (29)
- 2018年1月 (30)
- 2017年12月 (30)
- 2017年11月 (30)
- 2017年10月 (30)
- 2017年9月 (30)
- 2017年8月 (31)
- 2017年7月 (32)
- 2017年6月 (30)
- 2017年5月 (32)
- 2017年4月 (30)
- 2017年3月 (32)
- 2017年2月 (29)
- 2017年1月 (31)
- 2016年12月 (31)
- 2016年11月 (30)
- 2016年10月 (31)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (31)
- 2016年7月 (31)
- 2016年6月 (30)
- 2016年5月 (6)
- 2016年4月 (11)
- 2016年3月 (10)
- 2016年2月 (10)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (9)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (5)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (5)
カテゴリー別アーカイブ
- メディア報告 (3)
- 短所の向こう側に気づく (2)
- 褒めるために (3)
- 勉強の習慣をつけるために (3)
- 不登校を少なくするために (3)
- 不登校とHSP (3)
- HSP自己診断テスト (1)
- 不登校だった生徒の「その後」 (3)
- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)
- 子供が学校へ行かなくなったら (3)
- 親御さんからの質問 (6)
- 不登校をポジティブにとらえる (2)
- 「親の会」について (3)
- 高校認定試験について (9)
- 子供の自殺を防ぐために (2)
- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)
- 不登校の「親の会」の紹介 (8)
- イベントのお知らせ (99)
- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)
- LINE×家庭教師 (16)
- 安心して学校を休むために (2)
- 朝日新聞に掲載されました! (3)
- 集中力を持続させるために (1)
- 「不登校で長期欠席」最多 (1)
- 入試情報 (21)
- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)
- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)
- 発達障害と不登校 (2)
- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)
- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)
- 不登校 Q&A (9)
- 親の会でのひとコマ (9)
- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)
- 書籍案内 (15)
- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)
- 『居場所』 (2)
- 私立高校のご紹介 (10)
- 『話を聴いてもらう場所』 (3)
- 〝いま聞きたい人〟 (17)
- 高校体験入学 (1)
- 石川県総合模試のご案内 (27)
- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)
- メイクフレンズインタビュー (9)
- 石川県総合模試の結果 (10)
- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)
- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)
- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)
- 職業を知ろう! (3)
- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)
- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)
- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)
- アナログゲームのすすめ (2)
- 受け入れること (2)
- 不登校になった後の進路 (2)
- 不登校がもたらす『副産物』 (1)
- 家庭教師の日々あれこれ (1)
- さかなクンからのメッセージ (1)
- 不登校における親子の回復段階 (3)
- 高校受験はどうすればいい? (4)
- 動物が与える効果 (1)
- 一人一人に適した形を (2)
- 100%自分の意思で決断すること (3)
- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)
- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)
- 『いま』を大切に生きること (2)
- 「不登校に対する支援」について (3)
- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)
- 選べる『場所や時間帯』 (1)
- ゲーム(動画)依存について (3)
- 心のうぶ毛 (2)
- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)
- 『面接』も練習します! (2)
- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)
- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)
- ふさわしい伝え方 (2)
- スマホ・タブレットと共存する (2)
- 合格発表‼︎ (4)
- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)
- 自分自身が決断する人生 (3)
- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)
- 教育機会確保法とは? (2)
- 凧(たこ)の糸を引くように (2)
- 家の中に新しい風を入れる (1)
- ニンテンドースイッチ (1)
- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)
- 金沢市にある「フリースクール」 (4)
- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)
- 学校に行けなかった本当の理由 (2)
- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)
- 新年度へ向けて (1)
- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)
- 今日の出来事 (1)
- 3分ホームワーク (1)
- 「ありがとう」のチカラ (2)
- 新学期を迎えて (1)
- 子供のため?親のため? (2)
- 背中を押すこと (2)
- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)
- 不登校新聞のご案内 (1)
- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)
- 修学旅行ギャップ (1)
- 敏感だと感じる瞬間 (2)
- ファーストステップとして (3)
- 最近のニュースから (2)
- 20歳を過ぎて (2)
- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)
- 再び通学する生徒たち (2)
- HSCと不登校 (3)
- 『プラス1』の言葉 (4)
- 今回の放送の反響について (2)
- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)
- 会うことの難しさ (2)
- 聴いてもらうこと (2)
- 充実感 (2)
- 手紙 (2)
- 相手を肯定するために (2)
- 心がけるべき接し方 (2)
- メイクフレンズの新しい試み (3)
- 受け入れることの大切さ (2)
- HSCに関すること (4)
- 『親の会』に参加するメリット (2)
- 考えること、行動すること (3)
- HSCを知ることのメリット (2)
- 心のエネルギー (3)
- 一学期を振り返って (3)
- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)
- 特別支援学級について思うこと (2)
- 出発点として (1)
- いったん受けとめること (2)
- LINEを用いたアイスブレーキング (1)
- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)
- ネットゲームや動画について (2)
- 真の決断で、自立へ近づく (3)
- 生徒に会う前の準備 (2)
- 家庭教師に求められる役割 (2)
- 通信制高校について思うこと (2)
- 親にできることは? (2)
- 継続を自信につなげるために (2)
- フリースクールとの連携 (3)
- ホームエデュケーションについて (2)
- 〝安心の種〟をまこう! (3)
- 安心感を与えること (3)
- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)
- 積極的に待つこと (2)
- 調子が悪くなったとき (2)
- 親御さんにとって必要なこと (2)
- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)
- 自宅受験の意義 (2)
- モヤモヤの気持ち (3)
- 受験シーズンを前に (3)
- 一つの教科だけ (2)
- 問い合わせのメールから (3)
- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)
- 私立受験の心得 (2)
- 志望校を決めるにあたって (2)
- 2017年を振り返って (4)
- フリースクールのクリスマス会 (2)
- 2018年を迎えて (2)
- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)
- 3学期を前に思うこと (1)
- 初めての会場受験 (2)
- 新しい『居場所』を考える (3)
- 入試前夜 (2)
- 合格発表を前に (1)
- 豪雪でも。。 (1)
- 私立高校・合格発表を終えて (2)
- 改めて気付かされたこと (2)
- 定時制高校に合格するために (2)
- 成長の証 (1)
- 仮入学までに、今すべきことは? (2)
- メイクフレンズについて (1)
- 年度末に思うこと (2)
- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)
- 仮入学を終えて (1)
- 美容院 (2)
- 元気になったのは? (2)
- 正しい情報を得ること (2)
- 心の内 (3)
- 4月を迎えて (1)
- 課外授業 (1)
- 新しい学校生活に必要なことは? (1)
- 最初の週 (3)
- 入学して二週間 (3)
- coconoma カフェ (97)
- ちょうどいい場所 (3)
- ゴールデンウィーク明け (1)
- 再会から (3)
- 出席日数という圧力 (2)
- どんな状態であろうとも (4)
- みんなの居場所 (7)
- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)
- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)
- 今回の放送について (2)
- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)
- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)
- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)
- 『みんなの居場所』で出来ること (2)
- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)
- ドキュメント番組から思うこと (3)
- みんなの居場所NEWS (3)
- 2週間が過ぎて。。 (1)
- 『9月1日』問題へ向けて (4)
- 〝中間〟を目指す意味 (4)
- 毎日新聞に掲載されました! (1)
- 讀賣新聞に掲載されました! (1)
- ひきこもりを越えて (5)
- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)
- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)
- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)
- 読書するきっかけ (2)
- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)
- 新しい道へのサポート (1)
- 勉強再開への第一歩として (1)
- 一番の問題は。。 (1)
- 学校説明会に参加して (1)
- 連休明けに備えて (3)
- 4月を終えて。。 (1)
- 積み重ねていく大切さ (1)
- 10連休後の様子は。。 (1)
- 来週からテスト期間! (1)
- LINEで毎日の学習をサポート! (2)
- 通学できなくなったら。。 (6)
- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)
- みんなの居場所の活用法 (2)
- 講演会で話したこと (7)
- 英検準一級に合格! (1)
- 私立高校入試を終えて (1)
- お知らせ (7)
- 今年も全員合格でした! (1)
- 吐露カフェについて (2)
- 進路に関するあれこれ。 (1)
- 公立高校入試まで残り20日 (1)
- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)
- 新型コロナウイルスに関して (1)
- どのように生徒の安心を担保するか (3)
- 入試が終わって。。 (1)
- 『リモート家庭教師』始めました! (3)
- 褒めるときに意識すること (2)
- 入学式を前に (1)
- 生徒からの便り (1)
- 新学期が始まり。。 (1)
- りもかて(リモート家庭教師) (2)