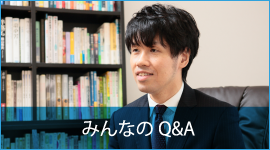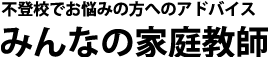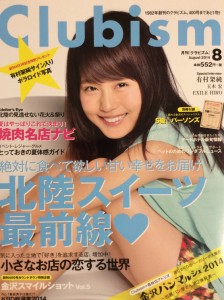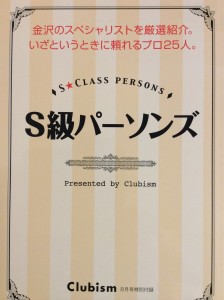活動報告
不登校を少なくするために❶
2015/04/07「不登校」という問題には、様々な原因が内在しています。
たった一つの原因だけで不登校になることは少ないです。
例えば、「勉強が分からないから」という一つの理由だけで不登校になるケースはほとんどありません。あるいは、「友達との関係が悪化したから」という理由だけで不登校になるケースも少ないです。
もし、それらの理由だけで不登校になるのであれば、もっと多くの生徒が不登校になっているでしょう。実際は、それらの問題に付随した悩みが複雑に絡み合って、結果的に不登校に結びつくケースがほとんどです。
仮に、「友達との関係が悪化してしまった」という悩みを抱えている生徒がいるとします。周囲に、その悩みをうちあける人間が誰もおらず、長期間にわたって、一人で悩み苦しみ続けることになったとしたら、学校へ行かなくなる可能性が出てきます。
一方で、友達であれ家族であれ、その抱えている悩みを真剣に聴いてくれる相手が周囲にいたならば、学校へ行かなくなる可能性は相対的に低くなるでしょう。
つまり、「友達との関係が悪化したこと」が本当の問題ではなく、「自分の悩みに耳を傾けてくれる存在、自分の気持ちに共感してくれる存在がいないこと」が一番の問題だともいえます。
とはいえ、同じような悩みを抱えていても、不登校になる生徒、ならない生徒が現実に存在します。
なぜでしょうか?
それは、不登校になりやすい生徒と、なりにくい生徒がいるからです。
次回は、不登校になりやすい方の特徴をあげ、その対策も含めて説明します。
勉強の習慣をつけるために❸
2015/03/30もう一つの利点は、生徒のやる気を持続させやすい点です。
家庭教師として週に一度伺う場合、今までは指導終了時に一週間分の宿題を出していました。 ほとんどの生徒は、「よ〜し、がんばるぞ」と、最初はやる気があります。
ところが、時間が経過するにつれて、やる気が薄れ自分に対して甘くなっていく生徒が出てきます。電話やメールをしたりして、宿題をすることを促したりもするのですが。。。
案の定、一週間後に指導に伺った時に確認をすると、宿題を全てしてなかったり、前日にまとめて宿題をしてしまったりということが、多くの生徒によって見受けられました。
これでは、毎日の勉強をコツコツ継続していく習慣がつきません。
一方で、「LINE×家庭教師」は、毎日宿題が送信され、添削されて戻ってきます。LINEを通して、毎日やり取りを行なうことで、生徒の勉強へのやる気を持続させやすくします。
なぜ、やる気が持続しやすいのか?
ある一人の生徒が、このように言っています。
「毎日の添削指導で、分からないところが分かったり、暗記を継続できたり、少しずつ前進できている感覚があるのがいい」
その結果、スモールステップの法則が実現しやすくなります。
背中を押されることで、少しずつ勉強を始める生徒も多くいます。そのような方には、この「LINE×家庭教師」はピッタリかもしれません。
勉強の習慣をつけるために❷
2015/03/24では、スモールステップを実現させるために、家庭教師として、どのようにサポートしていくのか?
「LINE×家庭教師」です。
つまり、スモールステップを実現できるように、LINEを使ってサポートします。
具体的には、次のような手順です。
⑴毎日、生徒一人一人に合った宿題をLINEを通して送信する。
⑵宿題終了後、生徒はそれを写真に撮り、家庭教師にLINEで送信する。
⑶送信してもらった宿題を添削し写真に撮り、なるべく早く生徒に返信する。
◎「LINE×家庭教師」の大きな利点は、二つあります。
一つは、LINEを通して生徒がどこで間違えやすかったのか、どの問題でつまずき分からなかったのかを、日常的に分析し把握することが可能になる点です。
そのため、家庭教師として指導する際に、生徒の今の状態を理解したうえで指導できるため、指導時間を最大限に効率良く使うことができます。
これまでは、毎回指導開始時に、前回設定した宿題をしっかりやっているかどうか確認するための時間が必要でした。その都度、指導時間中に間違っていたところ、分からなかったところを把握し対応しなければなりませんでした。
したがって、先生が宿題を確認し、その内容を把握している間、生徒は黙って待っている時間が多かれ少なかれ発生してしまいます。
そのため、貴重な指導時間の一部が実質的に目減りしてしまい、決して効率的ではありませんでした。「LINE×家庭教師」は、その問題点を解消するために、大変有効な方法になります。
「LINE×家庭教師」で、実質的な指導時間UPを実現!
次回は、もう一つの利点について説明します。
勉強の習慣をつけるために❶
2015/03/16「勉強の習慣をつけること」
これは永遠のテーマかもしれません。勉強の習慣をつけることが出来れば、きっと誰もが学力UPを手にすることでしょう。
勉強の習慣がつかない理由としては、集中力がない、誘惑に弱い、目標設定が甘い、ながら勉強を好むなど、いろいろ言われています。
では、家庭教師や塾を始めたら、その習慣がつくのか?
それは、生徒のやる気がゼロではないこと。それが絶対条件だと思います。やる気がある程度あれば、それを消さないように徐々に大きくしていき、習慣につなげることは可能だと思います。
では、どのようにしてやる気を大きくしていくのか?
例えば、スモールステップの法則があります。スモールステップの法則とは、いきなりゴールを目指すのでなく、生徒にとって実現可能な小さな目標を設定し、それをまず乗り越えることで達成感を味わいます。
次に、再び実現可能な小さな目標を設定し、それをまた達成し達成感を味わう。。。というふうに、それらを繰り返し、徐々にゴールに近付いていくというものです。
小さな目標を設定し、達成感を味わうことで、生徒のやる気は少しずつ大きくなります。やる気が大きくなれば勉強を継続しやすくなるので、その好循環を保てば勉強の習慣をつけることが可能になります。
スモールステップを成功させるためには、出来ることから始めることが大切です。例えば、計算や漢字など、簡単なもの、得意なものから始めることで長続きしやすくなります。
出来ることから始めることが、習慣づけの第一歩!
次回は、そのスモールステップを成功させるために、「家庭教師として、どのように生徒をサポートするのか?」について、明確な方法をあげて、より具体的に考えてみようと思います。
褒めるために❸
2015/03/08褒めるためにシリーズ、最後のポイントです。
◎「〜してくれてありがとう」
「ありがとう」と言われて、なぜ嬉しいのでしょうか?自分のしたことが誰かの役に立ったと思えるから嬉しいのだと思います。相手の存在価値を高める「ありがとう」は最強の褒め言葉です。家庭でも学校でも、どんどん「ありがとう」を言っていきましょう。
前回まで紹介したポイントのおさらいです。
◎「結果だけでなく、過程を重視する」
◎「他者と比較するのでなく、過去の本人と比較する」
◎「できた部分に注目する」
CASE❸小学6年生 男子
最近、料理に興味を持ち始めた息子。
休日になると、夕食の準備を手伝いたがることがしばしば。
でも、息子に教えながら料理をすると、一人で準備するより時間がかかってイライラしてしまう。そのうえ、不器用な包丁さばきを見ていると、危なっかしいと感じて料理に集中できない。
今日は日曜日。夕食の準備を手伝いたいと張り切っている息子。嬉しい反面、自分のペースで料理をしたいとも思う。
準備の途中、息子は不器用なりに丁寧に野菜を切っている。前回より上達している様子だ。
ところが、切った野菜をまな板から鍋に入れようとした瞬間、バランスを崩して、野菜がまな板から床にこぼれ落ちてしまった。息子が慌てて床に落ちた野菜を拾い始める。
今回も夕食の時間が遅れそう。。。
ここで、どのような言葉がけをしますか?
パターン①
「もっと注意しないとダメでしょ。落とした野菜、すぐに洗ってちょうだい。あんたに任せていたら、夕食の時間がどんどん遅れていってしまうわ」
〈改善すべき点〉
⑴失敗した部分に注目している。できた部分、よくなった部分に注目するべき。
⑵母親を手伝おうとする息子の一生懸命な姿勢に対して、「ありがとう」の言葉をかけるべき。
パターン②
「野菜は洗えば大丈夫だよ。前回に比べたら、包丁の使い方もよくなったね。最近よく手伝ってくれて助かる。今日も夕食の準備手伝ってくれてありがとね」
〈良い点〉
⑴前回の息子と今回の息子を比べて、上達した部分に注目して褒めている。
⑵夕食の準備を手伝ってくれたことに対して「ありがとう」を伝えている。
【まとめ】
野菜を床に落としてしまい、焦っている息子に対して、どんな言葉をかけるか?
前回と今回、手伝ってくれた時の息子を比べて、できた部分、よくなった部分を伝えることは、褒めるうえで非常に大切なポイントです。
切った野菜を落としたり、包丁の使い方にぎこちない点があっても、料理が上達している事実を伝えることで、息子の意欲は大きく膨らみます。失敗したことより、上達している過程に重きを置いて言葉がけをします。
そして、夕食の準備を手伝ってくれたことに対して、「手伝ってくれてありがとう」を伝えることは、子供の存在価値を高め、子供の自己肯定感を高めることに大きく貢献します。
次の休日も、きっと夕食の準備を手伝ってくれることでしょう。
褒めるために❷
2015/02/27今回の褒めるポイントです。
◎「結果だけでなく、過程を重視する」
前回紹介したポイントのおさらいです。
◎「他者と比較するのでなく、過去の本人と比較する」
◎「できた部分に注目する」
CASE❷中学二年生 女子
娘は軟式テニス部に所属している。一年生の時から放課後は練習に明け暮れてきた。
そして、迎えた秋の新人戦。昨日の一回戦と二回戦を勝ち、勢いに乗って臨んだ今日の三回戦。相手は数ヶ月前の試合で対戦したことがある強豪校。前回、娘たちは彼らに大敗したので、何としても今回は勝ちたかった。
しかし、善戦するも、もう一歩のところで惜しくも敗れてしまい、目標の優勝にはおよばなかった。試合に敗れた原因の一つは、試合の終盤に娘がいくつかのミスをしてしまったことだという。
夕方、落ち込んだ表情で帰宅した娘。。。
さて、どんな言葉がけをしますか?
パターン①
「試合の終盤で、あんなミスをするなんて練習が足りない証拠。同じ相手に二度負けるなんて恥ずかしいと思いなさい。どれだけいい試合しても勝たないと意味がないでしょ」
〈改善すべき点〉
⑴「結果」だけを重視している。今までの努力の「過程」を評価していない。
⑵できなかった部分に注目している。
パターン②
「試合には負けたけど、数ヶ月前の試合に比べたら、いいプレー多かったし、かなり良くなってたよ。今まで練習してきた成果が、今日の試合に表れてたと思う。体力は確実に増えたね」
〈良い点〉
⑴結果よりも、これまでの努力を評価している。
⑵「数ヶ月前の娘」と「現在の娘」を比較している。
⑶良くなったところ(できた部分)に注目している。
【まとめ】
試合に“勝つか負けるかの結果”で評価するのでなく、“どれだけ努力したかの過程”で評価することは、「努力をしよう」とする子供の意欲を引き出します。
白か黒か、0か100かで評価することは、「努力してもどうせムダだから」とネガティブ思考につながる原因をつくります。
反対に、どれだけ努力したかで子供を評価することは、ポジティブに物事をとらえやすくさせ、逆境を乗り越える勇気を子供に与える源になります。
例えば、いきなり大きな目標を設定するより、その都度小さな目標を設定して褒める機会を増やすことは、過程を意識させるために有効です。
褒めるために❶
2015/02/19今回は、日常で起こりうる状況下で、どのように接すれば褒める機会が増えるのかを考えてみようと思います。
今回の褒めるポイントは二つです。
◎「他者と比較するのでなく、過去の本人と比較する」
◎「できた部分に注目する」
CASE❶ 中学1年生 男子
テスト前の部活休みということもあり、早く帰ってきた息子。テスト前でも、前回は全く勉強しなかったのに、今回は自分の部屋で勉強している様子。
夕食時になり、母親が息子を呼びに部屋にやってきた。
呼んでも返事がない。集中して勉強してるのかと思い部屋に入ると、そこにはベッドに仰向けで眠っている息子が。。。
がっかりしながら起こした後、息子にたずねると、どうやら30分程度は勉強したという。
その後は疲れてベッドに横たわり、いつの間にか寝てしまったらしい。
さて、ここでどんな言葉がけをしますか?
パターン①
「せっかくテスト前の部活休みなのに、30分しか勉強しないで昼寝するって、何を考えてるん?お兄ちゃんなんて、帰ってきてから今までずっと勉強してたのに。それに比べてあんたときたら。。。」
〈改善すべき点〉
⑴兄と比較している。
⑵できなかった部分に注目している。
パターン②
「前回よりも、勉強がんばったね。普段は、ほとんど勉強しないのに、30分間も机に向かっていられただけでもスゴい進歩だね」
〈良い点〉
⑴兄との比較ではなく、過去の本人との比較。
⑵できた部分に注目している。
【まとめ】
パターン②は、兄と比較せず、過去の本人と比較しています。比較する場合は、このように他者と比較するのではなく、過去の本人と比較すると褒めやすくなります。少しの成長でも認めることによって、子供は「次はもう少しがんばろうかな」と意欲が出てきます。
もう一つは、できた部分に注目しています。できなかった部分に注目しても、褒めることは出来ません。たとえ、30分という短い時間でも、できた部分に意識を向けるから褒めることが出来るのです。
確かに、昼寝しているのを見たら、がっかりする気持ちは理解できます。もっとできるはずなのにと、できなかった部分を言いたくなりますが。。。
たとえ少しでも、できた部分をしっかり認める。それを積み重ねていくことが大切です。
次回は、CASE❷で新たなポイントも含めて考えてみようと思います。
短所の向こう側に気づく❷
2015/02/11「子供を褒めようにも、褒めるところがない。長所が見つからない」という声を聞きます。
褒めるためには、相手の長所に気づかなければなりません。その長所に、どのようにして気づけばいいのでしょうか?
そんな時、まずは短所に意識を向けてください。それから、その短所を違う角度から見るようにしてください。
例えば、周囲に鈍感な人がいるとします。
「あの人は空気が読めないし、本当にイライラする。かなりの鈍感だ」
確かに鈍感だと、周りの方にとってイライラする時があるかもしれません。でも、違う角度から見ると、どうなるでしょうか?
「鈍感ということは、物事に動じないし、ストレスも少なそうだ」
生きていくうえで、ストレスが少ないのは大きな利点ですね。このように、どこから見るかで印象がガラリと変わります。
ところで、なぜ短所が目につきやすいのでしょうか?
おそらく、ふだんから無意識的に、理想である誰かと比較していることが考えられます。比較してダメ出ししてしまうことによって、本来存在しているはずの長所を置き去りにしている、そんなふうに考えることもできます。
“他人と比較するのをやめる”
これは長所を見るために大切なポイントです。
「幸せとは、なるものでなく気づくもの」と、言われる方がいます。家族や友達の短所の向こう側に気づくことは、自分自身が幸せになるための第一歩なのかもしれません。
- 地味な→ 素朴な
- うるさい→ 元気、活気がある、にぎやかな
- 人の意見に左右されやすい→ 柔軟な
- 理屈っぽい→ 論理的な
- 芽が出ない、即戦力でない→ 大器晩成型である
- 不器用な→ 地道にがんばる
- 飽きっぽい→ 多趣味、好奇心旺盛な
- のろい、仕事が遅い→ 慎重な、コツコツがんばる
- マザコン→ 母親想い
- 派手な→ 華やかな、印象に残りやすい
- 鈍感な→ 物事に動じない、ストレスが少ない
- 悪趣味な→ 独特なセンス、個性的な
短所の向こう側に気づく❶
2015/02/03「不登校への対策」の中で、“短所を長所に変換して褒める”ことについて紹介しました。できない部分(短所)より、できる部分(長所)に気づくことが、褒めるうえでの基本姿勢です。今回から二回に分けて、一般的に知られている様々な短所を、魅力的な長所に変換していきます。すでに存在している、素晴らしい部分に気づくための助けになれば幸いです。
- しつこい→ 粘り強い、最後までやり遂げる
- 八方美人→ 誰とでも仲良くできる
- 行き当たりばったり→ 臨機応変に対応する
- 優柔不断→ 優しい、思慮深い
- 頑固→ 意志が強い、ぶれない
- 気が小さい→ 謙虚、慎重である
- 気弱で頼りない→ 温厚である
- 要領が悪い→ マイペースである
- 行動力がない→ じっくり考える
- せっかち→ 頭の回転が早い
- 堅苦しい→ 堅実である
- 強引→ リーダーシップがある
月別アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (5)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (1)
- 2020年9月 (3)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (7)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (21)
- 2020年2月 (29)
- 2020年1月 (15)
- 2019年12月 (16)
- 2019年11月 (16)
- 2019年10月 (20)
- 2019年9月 (17)
- 2019年8月 (16)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (24)
- 2019年5月 (33)
- 2019年4月 (15)
- 2019年3月 (14)
- 2019年2月 (11)
- 2019年1月 (10)
- 2018年12月 (11)
- 2018年11月 (20)
- 2018年10月 (22)
- 2018年9月 (38)
- 2018年8月 (43)
- 2018年7月 (28)
- 2018年6月 (26)
- 2018年5月 (21)
- 2018年4月 (23)
- 2018年3月 (24)
- 2018年2月 (29)
- 2018年1月 (30)
- 2017年12月 (30)
- 2017年11月 (30)
- 2017年10月 (30)
- 2017年9月 (30)
- 2017年8月 (31)
- 2017年7月 (32)
- 2017年6月 (30)
- 2017年5月 (32)
- 2017年4月 (30)
- 2017年3月 (32)
- 2017年2月 (29)
- 2017年1月 (31)
- 2016年12月 (31)
- 2016年11月 (30)
- 2016年10月 (31)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (31)
- 2016年7月 (31)
- 2016年6月 (30)
- 2016年5月 (6)
- 2016年4月 (11)
- 2016年3月 (10)
- 2016年2月 (10)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (6)
- 2015年10月 (9)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (5)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (5)
カテゴリー別アーカイブ
- メディア報告 (3)
- 短所の向こう側に気づく (2)
- 褒めるために (3)
- 勉強の習慣をつけるために (3)
- 不登校を少なくするために (3)
- 不登校とHSP (3)
- HSP自己診断テスト (1)
- 不登校だった生徒の「その後」 (3)
- 新法制定は「不登校を救う希望の光」となるか (2)
- 子供が学校へ行かなくなったら (3)
- 親御さんからの質問 (6)
- 不登校をポジティブにとらえる (2)
- 「親の会」について (3)
- 高校認定試験について (9)
- 子供の自殺を防ぐために (2)
- 不登校の生徒数が二年連続で増加 (1)
- 不登校の「親の会」の紹介 (8)
- イベントのお知らせ (99)
- 来週開催される「親の会」のご案内 (277)
- LINE×家庭教師 (16)
- 安心して学校を休むために (2)
- 朝日新聞に掲載されました! (3)
- 集中力を持続させるために (1)
- 「不登校で長期欠席」最多 (1)
- 入試情報 (21)
- 「やる気」はどこから生まれるのか? (1)
- 石川県/定時制高等学校の入試情報(平成28年度) (8)
- 発達障害と不登校 (2)
- 石川県/通信制高等学校の入試情報 (2)
- 今、不登校をふりかえって〜子供の視点と親の視点〜 (17)
- 不登校 Q&A (9)
- 親の会でのひとコマ (9)
- 『メイクフレンズ』〜同年代との交流〜 (5)
- 書籍案内 (15)
- 流行りのゲーム・アニメや遊び (10)
- 『居場所』 (2)
- 私立高校のご紹介 (10)
- 『話を聴いてもらう場所』 (3)
- 〝いま聞きたい人〟 (17)
- 高校体験入学 (1)
- 石川県総合模試のご案内 (27)
- 不登校を未然に防ぐために家族ができること (2)
- メイクフレンズインタビュー (9)
- 石川県総合模試の結果 (10)
- 『いしかわ県民教育文化センター』の通信に掲載されました! (2)
- 「おーぷんはうす・夏合宿」をふりかえって (4)
- 傾聴(アクティブリスニング)のすすめ (2)
- 職業を知ろう! (3)
- 職業を知ろう!No.1『客室乗務員(キャビンアテンダント)』 (7)
- みんなの家庭教師が、『みんなのニュース』で紹介されます! (3)
- LINEによる無料添削指導がもたらす効果 (1)
- アナログゲームのすすめ (2)
- 受け入れること (2)
- 不登校になった後の進路 (2)
- 不登校がもたらす『副産物』 (1)
- 家庭教師の日々あれこれ (1)
- さかなクンからのメッセージ (1)
- 不登校における親子の回復段階 (3)
- 高校受験はどうすればいい? (4)
- 動物が与える効果 (1)
- 一人一人に適した形を (2)
- 100%自分の意思で決断すること (3)
- 職業を知ろう!No.2『加賀象嵌(かがぞうがん)作家』 (6)
- たとえ「現在は」学校へ行けていても。。。 (2)
- 『いま』を大切に生きること (2)
- 「不登校に対する支援」について (3)
- 『一般社団法人LYHTY(リュフト)』のご紹介 (1)
- 選べる『場所や時間帯』 (1)
- ゲーム(動画)依存について (3)
- 心のうぶ毛 (2)
- 職業を知ろう!No.3『美容師』 (6)
- 『面接』も練習します! (2)
- 四コマ漫画を使って国語力UP! (2)
- 『見守り、待つ姿勢』を保つこと (2)
- ふさわしい伝え方 (2)
- スマホ・タブレットと共存する (2)
- 合格発表‼︎ (4)
- 学校に復帰しやすい環境をつくる (2)
- 自分自身が決断する人生 (3)
- 「学校第一」から「生徒第一」の姿勢へ (2)
- 教育機会確保法とは? (2)
- 凧(たこ)の糸を引くように (2)
- 家の中に新しい風を入れる (1)
- ニンテンドースイッチ (1)
- 職業を知ろう!No.4『ナレーター』 (8)
- 金沢市にある「フリースクール」 (4)
- 金沢市にある主な「通信制高校」 (6)
- 学校に行けなかった本当の理由 (2)
- どのように通信制高校を選択するべきか? (2)
- 新年度へ向けて (1)
- フリースクール「IRORI」の活動風景 (15)
- 今日の出来事 (1)
- 3分ホームワーク (1)
- 「ありがとう」のチカラ (2)
- 新学期を迎えて (1)
- 子供のため?親のため? (2)
- 背中を押すこと (2)
- 一秒でも早く学校に戻ってほしくて (3)
- 不登校新聞のご案内 (1)
- 『フリースクール リスタ金沢』を訪問して (2)
- 修学旅行ギャップ (1)
- 敏感だと感じる瞬間 (2)
- ファーストステップとして (3)
- 最近のニュースから (2)
- 20歳を過ぎて (2)
- みんなの家庭教師が、NHKで紹介されます! (4)
- 再び通学する生徒たち (2)
- HSCと不登校 (3)
- 『プラス1』の言葉 (4)
- 今回の放送の反響について (2)
- とても敏感な子どもへの言葉がけ (2)
- 会うことの難しさ (2)
- 聴いてもらうこと (2)
- 充実感 (2)
- 手紙 (2)
- 相手を肯定するために (2)
- 心がけるべき接し方 (2)
- メイクフレンズの新しい試み (3)
- 受け入れることの大切さ (2)
- HSCに関すること (4)
- 『親の会』に参加するメリット (2)
- 考えること、行動すること (3)
- HSCを知ることのメリット (2)
- 心のエネルギー (3)
- 一学期を振り返って (3)
- 待つべきか?働きかけるべきか? (2)
- 特別支援学級について思うこと (2)
- 出発点として (1)
- いったん受けとめること (2)
- LINEを用いたアイスブレーキング (1)
- とても敏感な子ども(HSC)との接し方 (2)
- ネットゲームや動画について (2)
- 真の決断で、自立へ近づく (3)
- 生徒に会う前の準備 (2)
- 家庭教師に求められる役割 (2)
- 通信制高校について思うこと (2)
- 親にできることは? (2)
- 継続を自信につなげるために (2)
- フリースクールとの連携 (3)
- ホームエデュケーションについて (2)
- 〝安心の種〟をまこう! (3)
- 安心感を与えること (3)
- 生徒たちを繋ぐ役割 (2)
- 積極的に待つこと (2)
- 調子が悪くなったとき (2)
- 親御さんにとって必要なこと (2)
- 一人一人にふさわしい環境を整える (2)
- 自宅受験の意義 (2)
- モヤモヤの気持ち (3)
- 受験シーズンを前に (3)
- 一つの教科だけ (2)
- 問い合わせのメールから (3)
- フリースクール リスタ金沢の活動風景 (3)
- 私立受験の心得 (2)
- 志望校を決めるにあたって (2)
- 2017年を振り返って (4)
- フリースクールのクリスマス会 (2)
- 2018年を迎えて (2)
- 失敗と書いて「せいちょう(成長)」と読む (2)
- 3学期を前に思うこと (1)
- 初めての会場受験 (2)
- 新しい『居場所』を考える (3)
- 入試前夜 (2)
- 合格発表を前に (1)
- 豪雪でも。。 (1)
- 私立高校・合格発表を終えて (2)
- 改めて気付かされたこと (2)
- 定時制高校に合格するために (2)
- 成長の証 (1)
- 仮入学までに、今すべきことは? (2)
- メイクフレンズについて (1)
- 年度末に思うこと (2)
- 仮入学前に、メイクフレンズ (2)
- 仮入学を終えて (1)
- 美容院 (2)
- 元気になったのは? (2)
- 正しい情報を得ること (2)
- 心の内 (3)
- 4月を迎えて (1)
- 課外授業 (1)
- 新しい学校生活に必要なことは? (1)
- 最初の週 (3)
- 入学して二週間 (3)
- coconoma カフェ (97)
- ちょうどいい場所 (3)
- ゴールデンウィーク明け (1)
- 再会から (3)
- 出席日数という圧力 (2)
- どんな状態であろうとも (4)
- みんなの居場所 (7)
- 北陸中日新聞・石川テレビ放送に掲載・放送されます! (1)
- 北國新聞、北陸中日新聞に掲載されました! (3)
- 今回の放送について (2)
- MRO北陸放送『レオスタ』、石川テレビ放送『石川さん プライムニュース』にて紹介されました! (1)
- HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト (1)
- 『守る』石川テレビ×北陸中日新聞 共同企画公式サイト (1)
- 『みんなの居場所』で出来ること (2)
- 『みんなの居場所』来週の営業時間 (49)
- ドキュメント番組から思うこと (3)
- みんなの居場所NEWS (3)
- 2週間が過ぎて。。 (1)
- 『9月1日』問題へ向けて (4)
- 〝中間〟を目指す意味 (4)
- 毎日新聞に掲載されました! (1)
- 讀賣新聞に掲載されました! (1)
- ひきこもりを越えて (5)
- 「#不登校は不幸じゃない」 (1)
- 高校入学後の彼らは?5カ月後の今は? (1)
- MRO北陸放送「レオスタ」にて、『みんなの居場所』が紹介されました! (1)
- 読書するきっかけ (2)
- 高校入学から5カ月後。彼らの『現在地』は? (7)
- 新しい道へのサポート (1)
- 勉強再開への第一歩として (1)
- 一番の問題は。。 (1)
- 学校説明会に参加して (1)
- 連休明けに備えて (3)
- 4月を終えて。。 (1)
- 積み重ねていく大切さ (1)
- 10連休後の様子は。。 (1)
- 来週からテスト期間! (1)
- LINEで毎日の学習をサポート! (2)
- 通学できなくなったら。。 (6)
- 『◯(まる)』が与える肯定感 (1)
- みんなの居場所の活用法 (2)
- 講演会で話したこと (7)
- 英検準一級に合格! (1)
- 私立高校入試を終えて (1)
- お知らせ (7)
- 今年も全員合格でした! (1)
- 吐露カフェについて (2)
- 進路に関するあれこれ。 (1)
- 公立高校入試まで残り20日 (1)
- Clubism(クラビズム)3月号に掲載されました! (1)
- 新型コロナウイルスに関して (1)
- どのように生徒の安心を担保するか (3)
- 入試が終わって。。 (1)
- 『リモート家庭教師』始めました! (3)
- 褒めるときに意識すること (2)
- 入学式を前に (1)
- 生徒からの便り (1)
- 新学期が始まり。。 (1)
- りもかて(リモート家庭教師) (2)